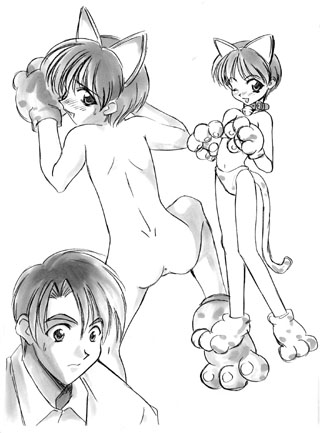「猫がやってきた!」 坂下 信明
雅人は勉強机の明かりをつけながら時計を見た。午後八時を少し回ったところだった。明日の模試は朝九時からだから、準備も合わせて七時半に起きれば充分だろう。ならば睡眠時間をたっぷりと取ったとしても、あと四時間は詰め込むことができる。
雅人は浪人生だった。東京の大学を目指し、挫折して、そのまま東京に居残っている。だが、遊ぶつもりで残ったのではない。雪辱を晴らすために、親に少し無理を言って、下宿を続けている。予備校通いの日々である。そして明日は、その予備校のクラスを編成するための模擬試験なのだった。これで失敗すれば、雅人の目指す大学ははるか彼方に遠のいてしまうだろう。雅人は、必死だった。
とりあえず数学の確認から始めようと参考書を開いた時、ドアのチャイムが鳴った。
「はーい」
(こんな時間に、誰だろう)
雅也は首を傾げながら、慌ててドアに向かった。ドアスコープさえ覗かずに、すぐに鍵を開けた。
「こんばんわー」
「あれ、美夜ちゃん」
立っていたのは、大家の娘、美夜だった。ショートカットにくりくりとした瞳が、妙に大人びて見える少女だが、実はまだ小学六年生のはずだ。背も実際よりは高く見えるので、雅人も初めは中学生だとばかり思っていた。
「おじゃましても、いい?」
「え、あと、どうしたの、こんな遅くに」
雅人は、少しためらった。こんな時間に、よそさまの娘を部屋に上げていいものか、自分の道徳観念に照らし合わせて、考えているのだ。
「あのね、いいもの持ってきたの」
そういって美夜は、大きめのボストンバッグを掲げて、にっこりと笑った。雅人はまじまじと美夜を見つめた。もう寒くはないだろうに、美夜は真っ赤なジャケットをしっかりと前まで閉めている。
(熱くないのかな)
そんなどうでもいいことを考えている雅人の横を、美夜はするりと抜けた。
「おじゃましまーす」
「あ、こら」
美夜は気にせず、居間に踏み込んだ。
「あれ、意外ときれいだね。雅人お兄ちゃんの部屋」
「意外とはなんだ、意外とは」
(まあ、きれいというより、ただ何もないだけだよな)
雅人は自分の部屋ながら、しみじみとそう思った。
「そんなことよりね」
ぱん、と美夜は手を打った。
「今日は、雅人お兄ちゃんの欲しがってたもの、持ってきたの」
そう言って美夜は、ボストンバッグを下に置いて、ごそごそと中をかき回した。
「僕の欲しがっていたもの?」
「そう。前話してたよね、ほら」
美夜がそうっと、それをカーペットの上に置いた。それは、よたよたと動きながら、みーみーと小さな声を出した。
「子猫だ! それもアメリカンショートヘアー!」
「ピンポーン、正解でーす」
雅人は急にしゃがみこむと、やさしく子猫を抱え上げた。まだ生まれて間もないらしく、子猫は怯えるように震えたが、雅人は「怖がらなくてもいいよ」と囁いた。
「かわいいなぁ。ねえ、これどうしたの?」
「お友達のとこの猫が産んだからって、もらってきたの。パパが誰かわからないから、純粋なアメショじゃないと思うけど」
「そんなの、どうだっていいよ。かわいければ」
そう言う雅人の様子を見て、美夜はくすっ、と笑った。
「なに?」
「だって、大人の男の人が、猫見てでれでれするのって、初めて見るもん」
「ふん、そう言われるのも慣れたよ」
雅人はつまらなさそうに、壁の方を指さした。
「その猫のカレンダーを見ていくだけでも、大抵のやつは変な顔をするな」
「だって、似合わないもん、ぜったい」
(子供ってのは、正直だね)
雅人は無言で、苦笑した。美夜はそんな雅人の思いを少しも気にせず、屈託のない笑いを浮かべている。
雅人は、美夜が嫌いではなかった。多少図々しくはあるが、それは子供特有のもので悪意はない。それよりも、ころころと変わる表情といい、よく動く瞳といい、どことなく雅人の好きな猫を彷彿とさせるのだ。気まぐれなところも、だ。だから雅人はよく、鍵っ子の美夜の話し相手になってやった。雅人の方も、相手が小学生とはいえ、かわいい少女と話をするのは楽しかった。
「だから、ちゃんとかわいがってあげてね」
急に美夜がそう話しかけたので、雅人は何のことかわからなかった。
「え?」
「いじめたりしたら、ひどいからね」
「え、え、飼ってもいいの? だってペットは規則で……」
「パパたちには、わたしから言っておくから、いいよ」
「ありがとう! 美夜ちゃん」
雅人は子猫を抱きしめたままで、美夜の手を握った。すると美夜は急に赤くなり、慌てて手を振りほどいた。恥ずかしそうに、背中を向ける。
「……あとね、もう一匹、いるの」
「え、どこに? 見せて見せて」
また美夜は、くすっと笑った。くるりと振り返り、上目づかいで雅人の顔を見る。
「雅人お兄ちゃんて、猫のことになると、ほんと子供みたい」
「うるさい、これでも気にしてるんだ」
「いいよ、雅人お兄ちゃんになら、見せてあげる」
生意気に、美夜はウィンクしながら囁きかけた。
「でもね、恥ずかしいから、ちょっとだけ、むこう向いてて」
「何で?」
「いいから、ぜったい、振り向かないって誓ったら、見せてあげる」
「どうして恥ずかしいの?」
「いいから、男は黙ってむこう向け!」
「はいはい」
雅人はくすくすと笑いながら、美夜に背中を見せた。すぐにごそごそ、と何かをまさぐる音がしたので、雅人も気になった。
(何だろう? 恥ずかしい猫って)
「ぜったい、ぜったいこっち見ないでよ」
「はい、絶対見ません」
一分ばかり、ごそごそと美夜が動く音が聞こえていた。その音がぱたり、と止んだ途端、ジーというファスナーの音がした。そしてかすかな、きぬずれの音。雅人はまさか、と思って抱えたままの子猫を見た。
「……もう、見ても、いいよ」
恥ずかしいのか、細かく震えた声がした。雅人はどきどきと高鳴る胸の鼓動を意識しながら、ゆっくりと振り向いた。
雅人の心臓は、止まりそうになった。
「にゃぁお」
そこに立っているのは、猫になった美夜だった。作り物の猫の耳をつけ、猫の大きな手袋とスリッパを履いている。しかし雅人の心臓を止めたのは、それだけではなかった。三毛の柄のきわどいビキニに、雅人の視線は吸い寄せられていた。
照れながら猫の鳴き真似をした美夜は、雅人が硬直したままなのを知り、慌ててしゃがみこんだ。
「あー、やっぱり変なんだぁ!」
「……いや、その、びっくりして」
雅人は我に返ると、視線のやり場に困った。しゃがみこんでいても、美夜の素肌はほとんど露出しているのだ。若々しくて艶のある肌は、それだけでも魅力的なラインを形成している。子供だとばかり思っていたが、胸や尻にも少しずつ、膨らみが見られた。それが三毛柄のビキニで強調されているのだから、別にロリコンでなくても唾を飲み込んでしまうような光景だろう。
「変なんでしょ! 似合わないんでしょ!」
泣きそうな顔になりながら、美夜はジャケットを掴んだ。もこもこの手袋をしているために、何度も掴みそこなって、やっとの思いでジャケットをはおった。その時、雅人は自分でも信じられないほどの声で叫んだ。
「ちょっと待って!!」
「え?」
美夜の動きが止まって、不思議そうに雅人を見上げた。雅人はゆっくりと子猫をテーブルの上に降ろしてから、美夜の前で同じようにしゃがみこんだ。
「ごめん、いきなりだったから面食らっちゃって、ちゃんとまだ見てないんだ。今度はちゃんと感想言うから、もう一回見せてくれないか?」
「……もう、いいもん。どうせ美夜には、こんなカッコは似合いません」
「そんなことないってば。ちらっと見た感じ、すごく魅力的だったよ。ほら、もう一回僕にちゃんと見せてごらん」
「……ほんと?」
「ああ、ほんとだよ。少し刺激が強かったけどね、僕には」
雅人は恥ずかしそうに頭をかいた。美夜はその様子を見て、くすくすと笑った。
「うん、じゃあわかった。でも、恥ずかしいからちょっとだけね」
美夜はいつもの明るさを取り戻して、立ち上がった。深呼吸をしながら、タイミングをはかるようにして一気にジャケットを脱ぐ。雅人の胸は、再び高鳴った。
「はい」
改めて見ると、美夜の猫姿はぴったりと似合いすぎていて、まるで本当に美夜が猫娘になってしまったのかと雅人は思った。美夜ははにかみながら、猫の手袋で頭をかく。そのしぐさまで、猫のようだ。それでいて猫と違うのは、毛皮が本当に最低限の部分にしかないことだった。すらりとした太腿も、すべすべとした腹も、思ったより華奢な肩も、眩しいような素肌がむきだしなのである。そして僅かだが脹らみつつある胸が、毛皮を押し上げている。手のひらですっぽりと隠れてしまうほどのサイズなのに、ブラが小さいのか、窮屈そうに収まっている。
「ねえ、どうなの?」
恥ずかしいのか肌寒いのか、美夜は前で両腕を組みながら訊いた。雅人はまた、固まったようにじっと美夜を見つめていたが、ついに耐えきれなくなったのか、急に美夜に飛びかかった。
「かわいい!」
「きゃっ!」
雅人はいきなり、美夜を抱きしめた。美夜は予想していたよりもほっそりとして、雅人の腕のなかにすっぽりと収まってしまった。美夜はそんな事態に困惑して、じたばたと抵抗するが、雅人の力は強く抜け出すことはできなかった。
「や、やめてよ。雅人お兄ちゃん」
「かわいいよ。うん、かわいい」
頬を赤く染めて抵抗する美夜だが、その声には力がなかった。かわいいという言葉が、思いのほか嬉しかったのかもしれない。だが、雅人は美夜を抱きながら、うっかりお尻を触ってしまった。途端に、美夜は身体を固くした。
「いやっ、エッチ!」
猫の手で、美夜は雅人を思い切り突き飛ばした。雅人はバランスを崩して、床に尻もちをつく。尾てい骨を激しく打って、雅人は悶絶した。
「いてっ!」
「あ、ごめんなさい!」
痛みで正常に戻った雅人は、腰をさすりながら、苦笑いで応えた。
雅人はコーヒーを入れた。ばつが悪そうにカップを美夜に渡すと、自分も座った。美夜は猫の手袋をしたままなので、両手でカップを受け取る。
「でも、どうしてそんな恰好を?」
「こんどね、学校で創作ダンスの発表会があるの」
美夜は猫舌なのか、じっとコーヒーの湯気を見つめたままで、説明した。
「テーマがね、動物なの。そいで、みんながわたしの名前からして、美夜は猫しかないよねってゆうから、わたしもその気になって、ママに衣装を頼んだの」
「それにしちゃ、ちょっと過激じゃない?」
「わたしも、そう思った」
美夜はへへ、と笑った。
「でも、ママはこんなのにしようねって、昼間仕事があるのに一生懸命ミシンかけてたから、わたしやだって言えなくなっちゃって。だけど恥ずかしいって言ったら、じゃあ誰かに見てもらいなさい、きっと色っぽくてくらくらするから、って言われたの」
「色っぽくて、ねえ」
(まだ色っぽい、っていうより、かわいいの方が強いよなあ)
雅人はぼーっと美夜を見つめながら、思った。すると美夜はその顔を覗き込むようにして、訊いた。
「ね、わたし色っぽかった?」
雅人は美夜の不安げな表情に、その色っぽさを急に感じて、戸惑った。ぐっ、と返答に窮する。
「ねえ、どうだった?」
「……まだ色っぽいっていうよりかは、ね。すごくかわいかったけど」
雅人はとっさに、そう答えた。美夜はその答えに不満のようで、頬を膨らませて横を向いた。
「ふーんだ、どうせ美夜はまだ子供ですよーだ」
「そ、そんなことは言ってないよ」
(まったく、すぐに拗ねたり、笑ったり、本当に猫みたいな娘だな)
雅人はテーブルの上でミルクを舐めている子猫と拗ねている美夜を交互に見やって、笑みを浮かべた。
「あーあ、雅人お兄ちゃんが抱きついてきたときは、悩殺してやった、と思ったんだげどなあ」
「あ、そのことは本当にごめん。あやまるよ」
意地悪く呟いた美夜に、雅人は頭を下げた。
「どうしようかなぁ、ママに言っちゃおうかなぁ」
「そ、それだけは勘弁して、僕、ここにいられなくなっちゃう」
「じゃあ、どうしてあんなことしたの? 教えて」
雅人が頭を上げると、美夜はにやにやしながら雅人を見下ろしていた。
(やれやれ、完全に向こうのペースだな)
仕方なく、雅人は説明した。
「僕はね、かわいいものを見ると駄目なんだ。自制がきかないんだ。いてもたってもいられなくなって、欲しくて堪らなくなる。だから、この歳になってもまだ、ぬいぐるみを買う癖がなくならないんだ」
「え、ぬいぐるみ持ってるの?」
美夜は不思議そうに部屋を見回した。どこにも、ぬいぐるみなどない。
「みんな実家だよ。結構場所取るからね。置いてきちゃったから、たまに寂しくなることがある」
「わたしにも一個ちょうだい!」
美夜が元気よく叫んだ。
「そうすれば、抱きつかれたことは誰にも言わない」
雅人はため息をついた。そうするしか、なさそうだった。
「わかったよ。今度帰ったら、とびきりのやつをプレゼントさせてもらうよ」
「わーい、やったぁ」
美夜がしてやったり、という顔で喜んだ。そしてそのまま、雅人にぐっと身を寄せて耳もとで囁いた。
「じゃあ、わたしはそのくらい、かわいかったの?」
雅人は美夜の吐息を感じて、耳まで真っ赤になった。美夜はそんな雅人を見て、面白くてたまらないように大声で笑った。
「あー、照れてる、おっかしー」
「こら、大人をからかうんじゃない」
平静を装うために、雅人は子猫を撫でた。ミルクを舐めるのに必死だった子猫は、いきなり撫でられたのでびっくりして、縮こまった。
「そんなことより、もうこんな時間なんだから、早く家へ帰りなさい。お母さんたちが心配するぞ」
「だって、今日は遅くなるんだって言ってたもん。まだ帰ってきてないよ」
そう言って美夜は、手を叩いた。すぐに手を叩くのは美夜の癖の一つだが、今は猫の手袋をしたままなので、ぼすん、という鈍い音しかしない。
「そう、忘れてた」
美夜は両手を合わせたままで、雅人に頭を下げた。
「先生、演技指導をお願いします」
「演技指導?」
ぴょこん、と猫耳を立たせて、美夜は微笑んだ。
「猫の動きみたいのを、教えて。雅人お兄ちゃんならそういうの詳しいと思って」
「まあ、少しくらいならできると思うけど、今日はもう遅いし、また今度に……」
「だけどわたしも塾とかあるし、雅人お兄ちゃんも予備校あるでしょ。今から教えて」
大きな目を潤ませて、頼み込まれると雅人も断り切れなかった。
「わかったわかった。ただし、少しだけだぞ」
「はい、先生」
ぺこり、と美夜はまた頭を下げた。頭の猫耳が揺れる。雅人は、その仕種がとてもかわいいと思った。
(いけない、また切れそうだ!)
雅人の心が、頼り無げに揺らいでいた。雅人はゆっくりと頭を振ると、テーブルの上のミルクの皿と子猫を奥の部屋に移動させて、テーブルを立てた。
「じゃあまず、猫のように四つんばいになってごらん」
「はぁい」
美夜は少し広くなった部屋で、何の疑問もなく四つんばいになった。立っている雅人からは、美夜のむき出しの背中が見える。今まで気にしていなかったが、お尻にはちゃんと三十センチほどのしっぽがついている。
「それで、今からは猫になりきるために、喋ってはいけない。猫は喋れないからね。すべて鳴き声で返事をすること」
「はい」
「違うだろ」
「みゃお」
美夜は楽しそうに、鳴いてみせた。雅人も満足げに頷く。
「じゃあ、まず僕に甘えてごらん」
「にゃあ」
美夜は四つんばいのままで、雅人に近づいた。雅人も腰を落とす。美夜がすりすりと身を寄せてくると、雅人は優しく頭を撫でてから、首の下をくすぐった。
「やっ、くすぐっ……みゃみゃみゃ」
「そうだ、猫はここをくすぐると気持ちいいんだよ。ほら、膝の上にも乗ってごらん」
「にゃあにゃあ」
ちょこんと膝に乗った美夜を、雅人はいとおしげに撫で回した。背中をさすりながら、雅人はいきなり、ブラの留め金を外してしまった。
「雅人お兄ちゃん! なにするの」
「おかしいな、この猫のおっぱいは二つしかないぞ。どっかに隠れてるのかな」
そう言って雅人は、くるりと美夜を仰向けにした。まだ小さい乳房が、あらわになる。美夜は恥ずかしそうに両手で隠そうとするが、雅人はそれを無理やり押しのけた。
「やめて、雅人お兄ちゃん」
「猫が喋っちゃいけないな」
雅人は美夜の胸に触れた。まだ幼く、固さの残る乳房をゆっくりと揉みしだく。ぽつりとした桜色の乳首に、そっと触れた。くすぐったいのか、美夜の身体がぴくりと反応している。抵抗する、力が緩んだ。雅人はその機を逃さず、一気に美夜を組み敷いた。
「かわいいよ。僕のものにしてしまいたい……」
「雅人、お兄ちゃん」
雅人は美夜の唇に自分の唇を重ねた。美夜は目を見開いたが、すぐにうっとりと目を閉じた。美夜の身体全体の、力が抜けていた。
唇が離れた。雅人の唇はそのまま首を伝い、乳房を吸った。両手は丹念に、美夜の腰のあたりをさすっている。やがて太腿へ、手のひらは移った。
「美夜ちゃん、脱がすよ」
「……うん」
美夜は目を潤ませて、頷いた。雅人はパンツをするりと下げると、美夜の右足だけを抜いた。脱がされた三毛柄のパンツは、左足首のあたりに引っ掛かったままになる。
雅人はぐっ、と美夜の脚を開かせた。美夜は顔を両手で覆った。
「……恥ずかしい、あんまり見ないで」
「まだ生えてないんだね」
つるりとした柔らかそうな肉に、亀裂だけが一筋、縦に走っていた。雅人は顔を近づけながら、指で亀裂を押し拡げた。きれいな赤い粘膜があらわになる。雅人は猫のように、ぺろりとそれを舐めた。
「あっ、いやっ」
脚を閉じようと美夜は力を込める。しかし雅人は太腿をしっかりと押さえており、美夜は身をずらすことさえできなかった。雅人は舌をもぞもぞと這わせて、やっと小さな突起を探り当てた。舌で突起を掘り起こすように愛撫する。すると美夜の声が、くぐもった響きを帯びるようになった。少し、鼻にかかった声だ。
「そうだよ、美夜ちゃん、猫はそうやって鳴くんだ」
「んなぉ、にゃうお」
美夜は未知の感覚にとまどっていた。知識としては、今自分のされていることは多少知っている。しかし自分でさえ触ったことのないところを舐められて、美夜は初めての快感を味わう余裕などないのだった。
それでも雅人は、美夜の亀裂の奥から、唾液ではない液体がしみ出てくるのを舌で感じていた。雅人はその液体があふれてくる隙間に、舌を差し込んでみた。思ったよりスムーズに、舌は奥まで滑り込んでゆく。
「にゃ、にゃ、おにい、ちゃん、やぁ、変なのぉ」
「変じゃないよ、それが普通なんだ」
雅人は舌を抜いて、美夜を抱き起こした。強く、抱きしめる。美夜も脱力しているが、ゆっくりと雅人の背中に腕を回した。
「美夜ちゃん」
「雅人お兄ちゃん、わたしのこと、好き?」
囁くように、美夜はそう問いかけた。雅人がこっくりと頷くと、美夜は笑顔で雅人にしがみついた。
「わたしも! ずっとね、好きだった。あの、受験の日なのに捨て猫にエサをあげてるのを見たときから、ずっと」
美夜が泣きそうな顔をするので、雅人は目に口づけをしてやった。
「わたし、美夜、雅人お兄ちゃんのことが好き」
「僕もだよ」
雅人の手が、再び太腿に置かれた。くるくると円を描きながら、次第に美夜の大事な部分へと指を這わせる。指先がそっと亀裂をなぞると、美夜は軽くのけ反って応えた。
「僕のものに、なろう」
美夜の耳もとで、雅人が囁いた。美夜は一瞬間を置いてから、頷いた。
「少し、怖いけど」
「じゃあ、また猫になろう」
雅人が、言った。
「発情期の猫に」
美夜はその言葉にきょとん、とした後、くすくすと静かに笑った。
「四つんばいになって」
美夜が雅人から離れて、おそるおそる四つんばいになった。雅人は美夜の柔らかな曲線を描くお尻の前で、ズボンを脱いだ。テントのようにぴんと張った、トランクスも脱ぎ捨てた。
「せっくす、しちゃうんだよね」
美夜の声が、震えている。雅人は言い返した。
「違うよ、交尾だよ」
「みゃぁお」
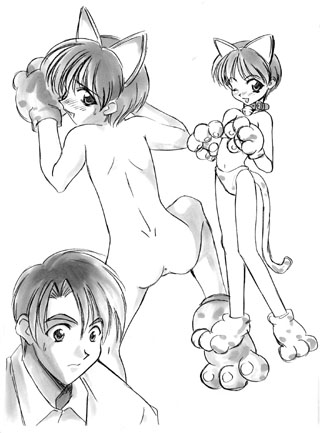
イラスト:河澄翔
おどけたように、美夜が返事をした。雅人は美夜の脚を少し拡げさせて、お尻を高く突き上げさせた。すると、美夜の恥ずかしい部分は、すぼまった肛門とともに、全くのむき出しになる。雅人は亀裂の中に、中指をゆっくりと差し入れた。ぬるぬるとした感触をまとわりつかせながら、中指は第二関節あたりまで飲み込まれた。なんとか、大丈夫そうだった。
「んんっ、あんまり痛くない」
「まだ指しか入れてないよ。今から、入れるからね」
指を抜くときも、美夜は声をたてた。段々と、快感がわかりつつあるのかもしれない。雅人は自分のペニスを握りしめると、亀裂にあてがった。ぐい、と一気に美夜の腰を引き寄せると、ペニスはずず、とめり込むように侵入を果たした。
「い、いたい、いたいよぉ」
「我慢して、もう少しだから」
「いや、いたい、もうやめてぇ」
痛がる美夜を気づかいながら、雅人はペニスを押し込んだ。半分ほど入ったところで、進むのをやめる。そこまでで、美夜の膣内はいっぱいだった。
「まだ痛い?」
「う、動かないでね、んっ、ちょっと」
美夜が泣きそうな声を出すので、雅人は手を伸ばして美夜のクリトリスに触れた。
「これ、気持ちいいだろ?」
「ふわっ、あ、あ、んくっ」
その反応で、雅人は美夜が感じているのを知った。クリトリスのあたりに触れたまま、腰をゆっくりと振り始める。かなりきつくて、気持ちがよかった。
「あああっ、わかんないっ、いたい、いっ、けど気持ちいい、はあっ」
「美夜ちゃん、はっ、もうすぐだからねっ」
雅人は次第に腰の動きを早め、そう言った。膣内はきつかったが、どんどんとぬるぬるがあふれてくるので、ペニスはよく動いた。もう、限界が近づいていた。
「あっ、出るっ!」
「んあっ、あついっ」
最後のひと突き、そして射精。びくんと震える雅人の腰に応えるように、美夜の身体も波をうった。
ふう、と息をつきながら雅人はペニスを抜いた。美夜は少しだけ、出血していた。血と精液が混じりながら、美夜の太腿を伝ってゆく。雅人はティッシュでそれを拭いながら、鼻唄でも歌いたい気分をなんとか押し留めていた。
(こんなにかわいい猫が一度に二匹も手に入るなんて、もう明日の模試なんてどうでもいいや)
奥の部屋から、よたよたと子猫が歩いてくるのを見ながら、雅人はニヤリと笑った。
終わり